
こんにちは 介護ラボのkanaです。今日は「認知症の理解」の中から『認知症の人の思いを尊重する』について、昨日と今日の2回に分けて書いていきます。
心地よさのサポートとは?
Contents
1.認知症の人の思いを尊重したサポート
1⃣生活習慣に沿った支援
2⃣自信を持たせる
(1)話したい
(2)自分で選びたい
(3)楽しみたい
2.当事者同士の出会いやメッセージの発信
3.心地よさのサポート
4.まとめ
1.認知症の人の思いを尊重したサポート
1⃣生活習慣に沿った支援
- その人がどのような職業であったのか
- どのように育ったのか
- 社交的であったのか
など、認知症発症前の本人のことを家族に教えてもらうことが重要です。
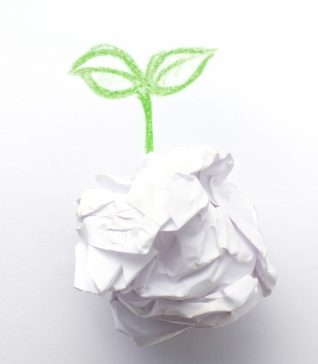
その際は、辛かったことなどの経験も聞いておきましょう。認知症で不安になった時に、その辛かった時の思い出とリンクして混乱している場合があります。
不安な気持ちを受け止めつつ、現在の困りごとが何であるかを探っていきましょう。
2⃣自信を持たせる

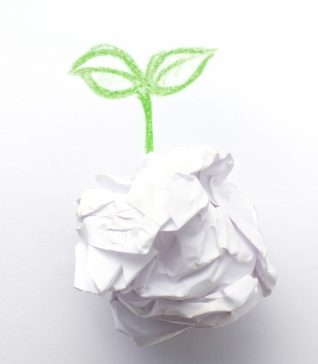
自分で出来ることが増えれば「自己肯定感」は増し、自分の持つ能力を最大限発揮することが出来ます。次項の3つのポイントを支援することが大切です。
※ 自己肯定感 :自分を尊重し、自らの存在を肯定する感覚のこと。自己肯定感が高いと、自分に自信が持て積極的に物事に取り組める状態になる。
(1)話したい
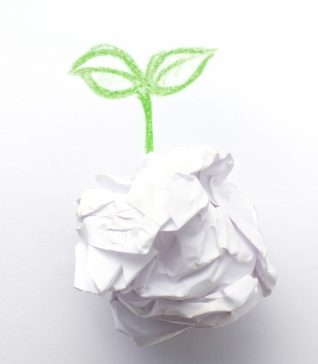
認知症の人に話してもらえるように、会話の糸口を作りましょう、興味のありそうな雑誌でもよいです。出来るだけ写真など視覚的に理解できるものが良いでしょう。
仕事や子育て、趣味に関することや、懐かしい回想法的な話題も、話を続けてもらうためには良いです。
その人の若い頃に何がはやったかを調べてみるのもよいでしょう。
- 歌
- 歌手
- スターだった俳優
- 髪型やファッション
- オリンピックや万博
- 家電
など、どのようなものが流行っていたのか、会話のきっかけを見つけることも大切です。
また、人に話を聴いてもらえることが、自分を価値ある存在と感じることにも繋がっていきます。会話としてあいまいで確実なことがわからない場合も「バリデーション」などの手法を使って、認知症の人が話したい気持ちを汲み取っていきましょう。

他の『バリデーション』記事はこちらから・・・
【バリデーションとは?】認知症ケア・6つの基本的態度と12の基本テクニック vol.397
(2)自分で選びたい

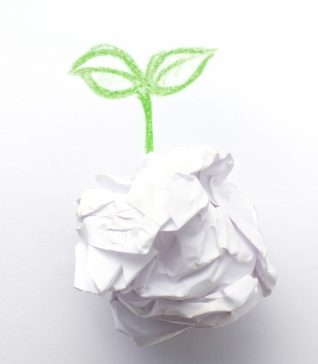
自分で選ぶ場面を多く持ちましょう。多くの中から選びにくい場合は選択肢を狭めて2~3個の中から選んでもらいましょう。
- 絵を書く場合に、絵の具の色や紙の色を選んでもらう
- コーヒーと紅茶という字を見せて、どちらにするか選んでもらう
- 同じお菓子でも自分で選んでもらう
このように、どうしたら選んでもらえるか考えることも大切です。
(3)楽しみたい

どういうことなら、認知症の人が楽しいことなのかを考えてみましょう。
「認知症の人にとって楽しい」こととは、介護者にとって楽しいこととは限らない場合もありますが、まずは介護者が楽しいと思うことを試してみてもよいと思います。
結果として楽しんでもらえなければ、そこから「なぜだろう」と考えてみましょう。
2.当事者同士の出会いやメッセージの発信
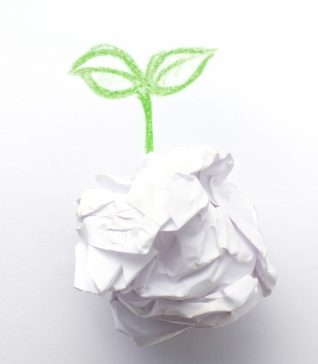
日本でも各地で「認知症の当事者交流会」が行われるようになってきました、特に診断直後に、当事者同時で出会うことが重要と言われています。
当事者と出会うことで、自分が思っていたより他の認知症の人が明るく過ごしている姿から、自分だけではないと気付くことが出来るのです。
認知症の人の中にも、「認知症になると何もわからなくなるのではないか」と思っている人も多く、初めて認知症の人に出会う人が殆どです。
そんな人がはじめて自分以外の認知症の人が元気であることを知り、前向きになっていきます。
最近は、認知症の人が認知症の人に相談に乗るといった「ピアカウンセリング」や、「認知症ワーキンググループ」のように施策への提言を行うグループも生まれています。
介護福祉職は、当事者同士で集まれる場づくりや、そういった場の情報を提供していくことが求められます。

3.心地よさのサポート

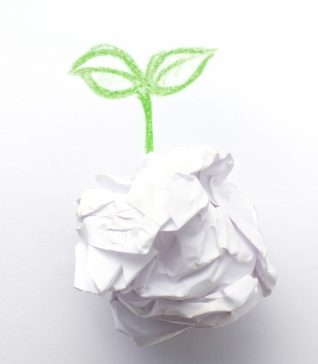
認知症が進行して寝たきりに近づいた時には、心地良さを重視した介護が望まれます。
- 認知症の人が気持ちよく休める寝具を用意したり、
- 好みの飲み物を好みの温度で用意したり、
- 好きなカップで飲み物を用意したり・・・
本人の希望を重視した「生活の継続性」を支援していくことが必要です。
4.まとめ
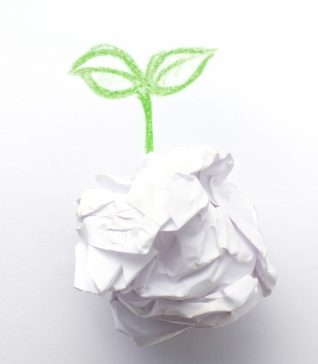
認知症の人が、『母が待っている』と亡くなった母を探して外に出ていくような行動をするようなら、「お母さんはどんな人でしたか?」「〇〇さんが頼りにしていた人だったのですね」など、寄り添う姿勢が大切です。
認知症の人は、今まさに母の所に行かなければいけない気持ちになっているので、過去のこととして思い出を語ってもらうことで、本人の不安に思っていることがわかることがあります。また、現在のことも認識しやすくなります。
このように、不安な気持ちを受け止めつつ、現在の困りごとが何であるのかを探ります。
また、否定せずに不安が過去のものであることをわかってもらえるような話し方を心掛けることにが大切です。

他の『認知症』記事はこちらから・・・
【認知症とは何か?】定義と診断基準、認知症状の全体像について vol.65
【①認知症の病理】脳の構造と症状との関係 vol.69
認知症の人の心理【不安・喪失感を抱く理由】vol.91
【パーソンセンタードケアとは?】5つの葉と3つのステップ vol.92
【①BPSDの定義】4つの分類と100以上の行動症状 vol.199
【②BPSD】5つの介入困難な背景要因と7つの介入可能な背景要因 vol.201
【③BPSD】11個の主要なBPSD・個別の背景因子について vol.202
【①認知症の中核症状とは?】記憶障害・見当識障害・遂行機能障害について vol.211
【③認知症の中核症状:失語・失行・失認】病識保持事例と病識低下事例の比較 vol.213
【認知症ケアの現状】基本的人権の理解と3つのケアの視点 vol.394
【認知症ケアにおける4つの関わり】事例を通して本人の望む生活と尊重した関りを考える vol.395
【バリデーションとは?】認知症ケア・6つの基本的態度と12の基本テクニック vol.397
⭐気になるワードがありましたら、下記の「ワード」若しくは、サイドバー(携帯スマホは最下部)に「サイト内検索」があります。良かったらキーワード検索してみて下さい(^▽^)/
ADL QOL グループホーム ケーススタディ コミュニケーション ノーマライゼーション バリアフリー ブログについて ユニバーサルデザイン 介護の法律や制度 介護サービス 介護予防 介護保険 介護福祉士 介護福祉職 他職種 住環境整備 入浴 入浴の介護 医行為 喀痰吸引 地域包括ケアシステム 多職種 尊厳 感染症 支援 施設 権利擁護 社会保障 福祉住環境 福祉住環境整備 福祉用具 経管栄養 老化 脳性麻痺 自立支援 視覚障害 認知症 誤嚥性肺炎 障害について 障害者 障害者総合支援制度 障害者総合支援法 食事 高齢者
に参加しています。よかったら応援お願いします💛
Twitterのフォローよろしくお願いします🥺
