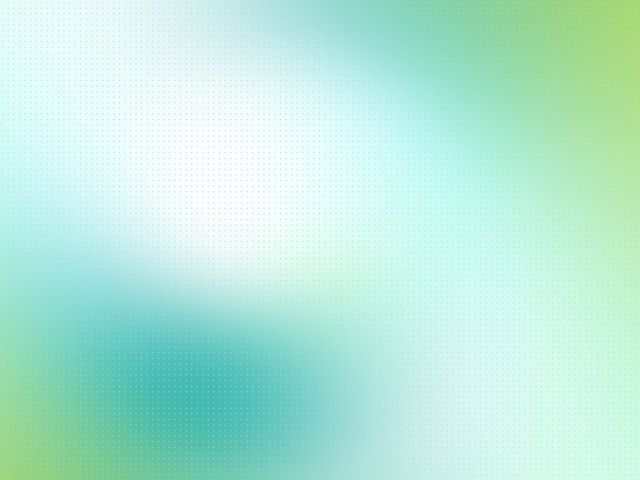
こんにちは(^▽^)/ 介護ラボ・kanalogのカナです。今回は・・・
目を構成する大な部位とその働き
✅介護ラボのトップページ(介護について色々なカテゴリーをまとめています)🌟
✅介護ラボ・辞書のトップページ
目の構造と機能
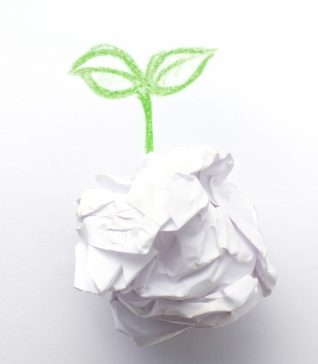
「眼」は・・・外界の光による多くの情報を受け取る感覚器です。感覚器が受け取る情報の約8割が眼からの情報だと言われています。
眼の重要性は、目が頭蓋骨の中の眼窩と呼ばれるくぼみにあり、その周囲を脂肪組織が囲み外界からの衝撃から保護されるように位置していることからもわかります。

眼球は、直径25mm、重さ約8gほどのほぼ球形です。
(1)見えるしくみ

外界からの光は、角膜、前眼房に入ります。
眼はカメラによくたとえられますが、「虹彩」はカメラの絞りのような働きをしています。ピントを合わせるのが「毛様体」で、その筋肉組織を伸縮させて水晶体の屈折力を調整しています。
外界からの光の刺激は「硝子体」を進み、「網膜」で映像を結び、視神経を刺激し、大脳の視覚中枢に伝えられ、色や物の形を整える働きをしています。大脳の視覚中枢は後頭葉に位置しています。
視神経が大脳にいたるまでに、左右網膜からの視神経は、頭蓋内で交差する部位があり、それを「視交叉(しこうさ)」といいます。
視交叉では、網膜の内側部分(鼻側)からの神経線維だけが交差しています。これは物を立体的に見るためのしくみとされています。
(2)目を構成する大な部位とその働き
- ✅目の9部位とそのはたらき
- ■角膜
厚さ0.5~1mmの透明な膜
眼球全体を包む外膜の前方6分の1の無色透明な部分。知覚に敏感で、角膜反射等で眼を保護する働きがある
■強膜
後方6分の5の白目の部分
眼球を保護する膜
■毛様体
水晶体とつながっていて、水晶体の厚さの調整をする
(ピントを合わせる役割)
■虹彩(ブドウ膜)
水晶体の前に縁どるように円状に位置しており、光の量を調整する働きがある。日本人は茶褐色をしている。
中央部を瞳孔といい、明るいと小さくなり、暗いと大きくなる(カメラの絞りのような役割)
■脈絡膜
強膜の内側に位置し、血管と色素に富む膜
■網膜
視細胞と視神経を含む、柔らかく剥離しやすい膜
■水晶体
瞳孔の後ろにあり、直径1cm。無色透明で弾力性がある。血管や神経は分布していない。レンズのはたらきをしている。
■硝子体
水晶体と網膜の間を満たす、無色透明でゼリー状の物質。眼球の内圧を保つ働きをする(栄養を与える)
■眼房(眼房水)
透明の液体で、水晶体と角膜の間を満たして、水晶体・硝子体・角膜に栄養を与えるはたらきをする。眼圧を一定に保つ働きをしている。眼房は「前眼房」と「後眼房」に区別される
- ✅副眼器4部位とそのはたらき
- ◆眼瞼
上下2枚のヒダで、外面は皮膚、内面は結膜に続く
眼球の保護や光刺激の調整を行う働きがある
◆結膜
眼瞼に続く粘膜で、血管や神経に無部分。眼瞼のはたらきを円滑にする働きがある
◆涙器
涙腺から分泌された涙は眼球前面を潤し、最終的には鼻腔に流れる
◆眼筋
眼球運動をつかさどり、6対の筋からなる
脳神経である「動眼神経」「滑車神経」「外転神経」により支配されている
「介護ラボ」の人気の記事
介護に困ったときに知っておきたいこと(相談窓口・手続き)
介護保険で利用できる『7つの介護予防プログラム』を使って自立した生活を継続しよう!
【ピアジェ、エリクソン、ハヴィガースト】発達段階と発達課題 vol.77
【比較】エンパワメントとストレングスとは?介護福祉職による支援方法 vol.45
【老年期】ハヴィガースト、エリクソン、ペック、レヴィンソン、バルテスの発達理論 vol.283
【介護福祉の基本理念・ポイント3つ】最も大切な理念とは? vol.8
【障害受容の5つの段階】障害者を取り巻く4つの障壁(バリア)vol.49
【発達理論】ピアジェ、エリクソン、バルテスの発達論を理解する vol.76
【アセスメントの3つの視点】情報の解釈、関連付け、統合化とは? vol.195
(3)その他のはたらき

眼は眼球以外に、前項に書いた副眼器と呼ばれるもので構成されています。
副眼器の1つである眼瞼(まぶた)が行うまばたきは、無意識のうちに1分間に約15~20回行われ、それとともに分泌物(涙等)によって角膜を潤す働きがあります。
眼で見ることのできる範囲を「視野」といい、視野は1点を見つめている時に、上下左右同時に見える空間をいいます。
この他には、「光覚(こうかく)」という光を感じその明るさの差を判断する機能と、「色覚」という色を判断する機能があります。

に参加しています。よかったら応援お願いします💛
良かったらTwitterのフォローお願いします🥺
