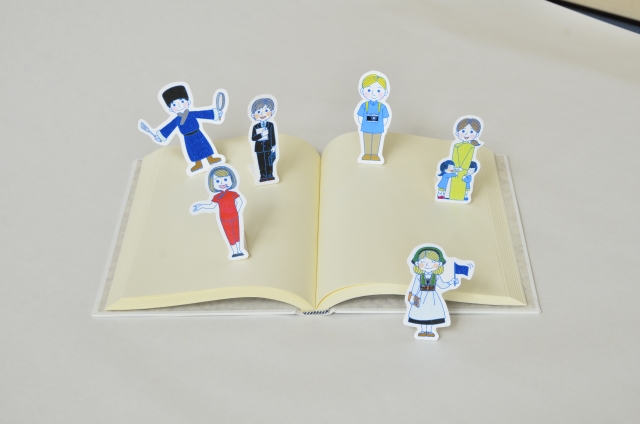
こんにちは
介護ラボ・kanalogのカナです💚 今回は・・・
多くの呼び名がある『個別援助計画』について
✅介護ラボのトップページ(介護について色々なカテゴリーをまとめています)🌟
✅介護ラボ・辞書のトップページ
生活支援における介護過程の意義

「1人の人間として自分らしく」という生活支援を目指すためには、1人ひとりをよく理解することが重要となります。そのうえで、介護計画にその人らしさが反映された個別ケアを提供できるよう、介護過程に基づく介護実践が不可欠です。
「生活支援における介護課程の意義って何?」
利用者の生活は、現時点だけではなく、これまでの生活の上に成り立っています。さらに現在の延長線上に未来があるというように、生活を継続できることが重要です。
1日の生活を例にとっても分かるように、24時間の生活支援を、1人の介護福祉職だけで役割を果たすことは不可能です。そのため介護福祉職の活動は、チームによって支援を行います。
しかし、チームメンバーによって、利用者のとらえ方が1人ひとり異なる状況では、利用者の状況に応じた介護の実践を提供することはできません。
チームで利用者の状況に応じたより良い介護実践に取り組むためには、チームの介護実践の根拠となる介護計画の存在が重要になります。
なぜなら、介護計画をよりどころに、チームで統一された介護を実践できるからです。チーム活動としての介護実践を共有するためのツールが介護過程における介護計画なのです。
介護過程と事前検討

介護過程が、チーム活動として行うものならば、その活動能力を高めるためには、
『事前検討』や『事例研究』
が必要です。
事前検討や事例研究によって、利用者についての理解を深めることができます。また、これらを行うことは、チームで取り組んでいる自らの介護実践そのものを振り返る機会にもなり、積み重ねることによって、チーム全体の介護実践の質を高め、ひいてはよりよい個別ケアの提供に繋げることができます。

(1)5つの事前検討方法

日常的に用いられる方法が「事例検討」と呼ばれています。これは、ケアカンファレンス、ケースカンファレンスなどと呼ばれることもあります。
検討の題材となるのは、特定の介護活動や困難な介護事例(例えば、家族介護者に精神障害があるなど、検討しなければない課題が多かったり複雑だったりして解決が難しい事例)など様々です。
まず、事例検討の開催にあたっては、日時や場所、テーマなどを予告し、チームメンバーが参加に向けた調整や準備ができるよう配慮することが大切です。それを踏まえて、5つの概要をまとめます。
①事例の提示
事例提供者から、事例の概要と、その事例を選定した理由、そして検討してほしい点などについて説明します。その際、チームメンバーが理解できるよう、必要に応じて資料を作成するなど分かり易い発表のための工夫も必要になります。
②事例の共有化
チームメンバーは、事例提供者に質問をして、事例の理解と事例提供者の意図について、イメージを共通できるよう情報の整理をします。
③論点の明確化
事例の共有が出来たら、検討すべき論点をチームで整理し、いくつかに焦点化していきます。
④論点の検討
限られた時間の中で、検討すべき論点についてディスカッションを行います。必要な時には優先順位をつけ、この段階で何を検討するのか、論点を整理しながら進めます。
ここで重要なことは、メンバー間での自由な意見交換ができる雰囲気作りです。日頃から安心して意見を言える人間関係が形成されているかどうかが、事例検討の場にも影響します。
様々な意見交換によって、事例に対する今後の対応の在り方について、具体的な結論が得られるよう検討を行います。
⑤まとめ
事例検討の内容を整理し、最終的なまとめをします。
このような事例検討を定期的に、また必要に応じて開催し、チーム全体で検討、共有していくことで、チーム全体の質が高まります。
(2)事例研究の意義
組織としてのチームを育てるという観点からは、事例検討も効果的ですが、事例研究は更に高い効果が得られます。

事例研究は、事例検討から得られる結果から、他の事例にも応用が効くような、より良い支援の方法を考えたり、原理原則を導き出したりと、より学問的な側面を持っています。
研究レベルで、チームの介護活動を深く掘り下げて介護実践の原則を見いだす、実践の評価を深める、また日頃の疑問を解き明かす取り組みなどにチャレンジすることで、介護福祉職としての成長だけでなくチーム全体の活性化に繋がります。チームの一員としてのメンバーシップ、リーダーシップ能力を高めることにも繋がります。
「介護ラボ」の人気の記事
介護に困ったときに知っておきたいこと(相談窓口・手続き)
介護保険で利用できる『7つの介護予防プログラム』を使って自立した生活を継続しよう!
【ピアジェ、エリクソン、ハヴィガースト】発達段階と発達課題 vol.77
【比較】エンパワメントとストレングスとは?介護福祉職による支援方法 vol.45
【老年期】ハヴィガースト、エリクソン、ペック、レヴィンソン、バルテスの発達理論 vol.283
【介護福祉の基本理念・ポイント3つ】最も大切な理念とは? vol.8
【障害受容の5つの段階】障害者を取り巻く4つの障壁(バリア)vol.49
【発達理論】ピアジェ、エリクソン、バルテスの発達論を理解する vol.76
【アセスメントの3つの視点】情報の解釈、関連付け、統合化とは? vol.195
(3)介護福祉分野で使用する『計画』

介護福祉分野で使用する「計画」には、
- 「介護計画」
- 「個別援助計画」
- 「個別サービス計画」
- 「ケアプラン」
など、同一の「計画書」に対して複数の呼び名があり、その違いが分かりにくい状態にあるのが現状です。
介護計画の立案について考える前に、それらの言葉の整理をします。
❶ケアプランとは
ケアプランは、利用者を支援する際の全体的な支援の方向性と、訪問介護や配食サービスなど、必要となる社会資源をどのように提供すればよいかを記載した計画書の事です。

ケアプランという呼び方は法律で決められた正式名称ではなく、介護保険法上では『介護サービス計画』と呼びます。
そのうえで、介護保険施設におけるケアプランという場合は、「施設サービス計画」、居宅においては「居宅サービス計画」と呼ばれています。
また、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、障害者総合支援法)におけるケアプランは「サービス等利用計画」と呼ばれています。
ケアプランは利用者本人や家族なども作成できますが、実際には多くの場合でケアマネジャーという専門職がケアマネジメントという手法を使って作成しています。
❷個別援助計画とは
個別援助計画は、ケアプランに位置づけられたサービスを具体的にどう実施していくかを定めた計画の総称の事です。
例えば・・・

ケアプランに「訪問看護」が位置付けられた場合・・・
看護師は訪問看護の個別援助計画として「訪問看護計画」を立てます。

ケアプランに「訪問介護」が位置付けられた場合・・・
介護福祉士が訪問介護の個別援助計画として「訪問介護計画」を作成します。
介護保険法上、個別援助計画は「個別サービス計画」という言葉が使われています。
このように、個別援助計画には多くの呼び方があることから、混乱しないように注意する必要があります。
に参加しています。よかったら応援お願いします💛
良かったらTwitterのフォローお願いします🥺
